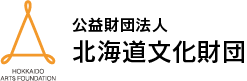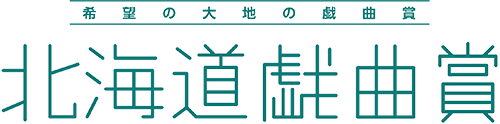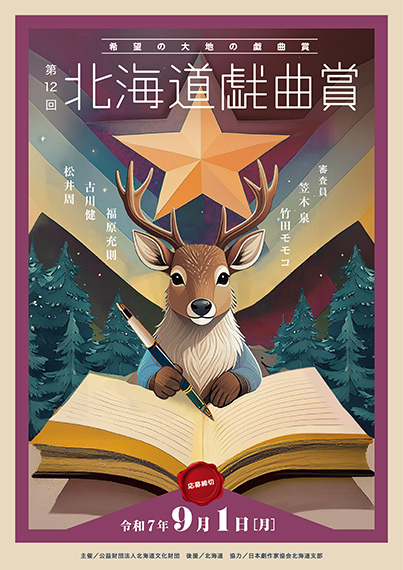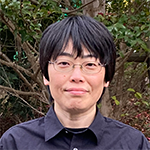今年で二度目の参加、大賞と優秀賞が三本出た昨年が私にとって初めての北海道戯曲賞です。だから基準が厳しくなっていると思うのですが、今年は「好き」と思う戯曲はあっても、大賞に値する作品かと考えたときに迷ってしまいました。
あるいは、どうしたって好き嫌いで読んでしまう部分はあるのだから、個人的な想いでも激しく推せるものがあればよし、とも思うのです。ただ今回はすべての候補作を読んでもそこまでの熱量に至らず、突き動かされるようなものに出会いたかったという思いが残りました。
たまたま今年の傾向なのか、短いシーンをコラージュし、時間や空間をずらしたり、前後にねじったりする作品が多かったように思うのですが、その手法自体は面白いところがあると思うものの、複雑なプロットに対して台詞が追いついていない印象がありました。
設定や背景の状況を曖昧な会話でぼやかす、というやり方が乱雑に使われすぎていないかと思ってしまったのです。
プロットを工夫するうえにも、生きた言葉が必要であること。それらを丁寧に、根気強く、豊かに紡ぐ作業を見たい。と、これは同じようなスタイルで書くことがある私自身へも向けた自省の念です。
以下、そうしたこともふまえ、すべての作品に触れてみます。
『さよなら、サンカク』は過去と現在を行き来する構成に確かな技術を感じる一方、冒頭で家族構成を説明するためにやたらと説明台詞が続いてしまうのが勿体ないと思いました。
主人公の女の子が置かれる状況が恐ろしく悲惨であることは想像できるし、名前を取り戻すシーンもジンとしました。が、人格崩壊を起こしてしまう前の、元がどんな子だったのかをもっと知りたかった。これだけ重い題材を扱うなら、彼女の人生を覚悟して背負ってほしいです。そうでないと、ただ悲惨な目に遭った子がどう再生するのかを描いてみました、というショック&感動ポルノに留まってしまう気がするのです。
昨年も優秀賞を獲った本橋さんの『さなぎ』は、大晦日から年明けまでの数時間を切り取り、日本と異国、時差のある二つの空間を重ね合わせるというアイディアがとても魅力的でした。
ただ、そこで出てくる「曖昧な会話」は、時間や空間をシームレスにするためあえてそうしている体なのだけれど、もしかすると作者が掘っていないところを都合よくぼやかしているのでは?と訝ってしまうところもありました。
また、ジロウ、テツ、父という一つの軸を構成している家族が、三人とも共通して女性との距離の詰め方にある種の幼さを感じ、反して女性の登場人物はやや類型的に見えました。描き分けの偏りを独自の個性とみるのか、視野の狭さとみるのかという点で、今作に関しては後者に感じ(昨年は魅力に映ったのです)、大賞に推すことはしませんでした。
でも、すでに作者の持ち味というものが確立していて、それ自体がすごいことだと思います。だから優秀賞に異論はありません。
『須磨浦旅行譚』
会話のところどころが虫食いになっているようで、1ページ読み飛ばしちゃったかなと何度も引き返す作業で読むのに苦労しました。あらすじがないとわからないストーリー、あまりにも主語がなさ過ぎる会話は、作者の自己完結が過ぎるのでないかと思います。ただ、それが効果的に見えるような、光る会話もありました。そして徐々にその文体に慣れていくと、車内から海を眺め、古墳や食堂に立ち寄りオムそばを食べ公園にたどり着くだけのちっぽけなロードムービーが、不思議と心惹かれて楽しかったのです。なにげないのに忘れられない、ある一日を切り取る目線に味わいがあり、演出してみたいとちょっとだけ(技量を試されますが!)思いました。
『ハイライト』
かつて多くの地方出身者が憧れた東京はもう存在せず、崩壊してしまった町の中で人のなりをした交通安全ロボットだけが手を振り付けている、という絵。さびしくもどこか間の抜けた姿を想像してわくわくし、そんな安全太郎に恋をする女という設定にどきどきしました。ところが、どんな変態的な恋物語になるかと思いきや、そこはさほど描かれていなかったので少し残念に思いました。
前回大賞に選ばれた『バージン・ブルース』同様、限られた人数でテンポよく空間を移していく自由自在で軽やかな筆致は作者の強い武器なのだなと思います。
ただ今回はいつまでも軸が見えないまま強引に場所や時間を飛ばされていく感覚でした。
全員希薄な関係性の登場人物だけで構成するストーリーにおいて、彼/彼女らがどう近づいていくのかという過程は重要な牽引力だと思うのです。そのあたりが端折られていて、いつの間にか皆が当たり前にわいわいとおしゃべりし始めたので、どこへ行き、何をしていても、すべてが「ごっこ遊び」のようなところで停滞してしまい、彼らの過ごす特別な夜を深く追いかけられなかったのです。
『私 ミープ・ヒースの物語』
ゆがんだ政治思想に慣らされていく人々への不安や恐怖、信念を貫こうとしながらも迷い葛藤するミープの姿を今、この時代に描くことには意義があると思いますし、真摯に物語を描く姿勢に好感を持ちました。それでも読むほどに重複した解説がくどく感じてしまいました。教科書を読んでいるようで、生きた会話を感じにくく、理解はできても個人の抱く想いへの共感までには至らなかったのです。終盤、ラウラとの関係があそこまで大きなものになるならば、はじめからミープとラウラの友情関係に焦点を絞ってもよかったのではないでしょうか。この関係こそが今作の最大の魅力だと私は思いました。二人の幼なじみが、時代のうねりのなかでどう変化していくのか。そこを克明に追っていくことで彼女たちを取り巻く社会も見えるでしょうし、もしかすればアンネが登場しなくても良いくらい、オリジナリティのある芯の強い作品になるかもしれません。
『あいがけ』
今年の候補作のなかで、私にとって最も「ちょうどいい」対話の距離感を感じたのがこの作品でした。虚無的な礼司と異国からやってきたマレーシア人・アニ、喪失を抱えた寄る辺なきもの同士が、頼りない糸をたぐり寄せるような会話がとてもよかったです。芝居の狭間でガタガタときしむ家、礼司の妹・敬子のかさついた心に水がたまっていくような雨の描写も印象的で、やわらかく沁みる読後感がありました。
私はこの作品が好きです、という想いでささやかに推しましたが、賛同は得られませんでした。そこをなんとか、ともう一歩強く推せなかったのは、アニが純真に描かれすぎなのでは?というほかの審査員の方々の意見に納得してしまったからでもありますし、出てこない人物の設定が複雑すぎるという声に対し、その必要性を私も強く主張できなかったからです。
世捨て人のような礼司が単に私好みの色気を発しているだけなのかしらん…などと考えてしまったりもしました。でも、色気のある台詞が描けるってすごいことですよね。
『害悪』
人工知能が指揮するAI戦争だとして、なぜ兵士は生身でなくてはならないのか?戦没者が出た場合そっくりなアンドロイドを贈るなら、はじめからアンドロイド同士で戦えばいいじゃないか?と、冒頭の設定からしてうまく乗れずにいました。だから、実はこれこれこうで…と種明かしが来ても、むしろなぜ人々は最初にそこを疑わなかったんだ、とつっこんでしまいました。
劇場をどう使うか立体的に想像して書いている本で、現代的な会話のリズムにセンスを感じます。挑発的な台詞の数々も、アバンギャルドに攻めていく作風として突き詰めればこれからもっと面白くなりそうな気がします。でも、どの人物もやたらと他者を馬鹿呼ばわりするのは、露悪的に見せているのだとしても語彙が足りないのではないかと思います。
『Share シェア』
ボケとツッコミの応酬はちょっと疲れながらも楽しく、ここまで関西ノリが満載のワンシチュエーション芝居は一周回って新鮮にも思いました。ベタながらも愛すべき住民たちのやりとりに何度も笑いました。早希はさばさばしている部分と脆さのバランスが魅力的で、周りがほっとけないのがよくわかります。
とぼけた明るい会話の中に普段は埋もれている悲劇が、時折誰を傷つけるためでもなくぽっと立ち現れる様も、ほとんどうまくいっていたように思います。ただ、最も深い傷に触れる温泉旅行のくだりを故人である香織に夢のなかで語らせてしまったところは惜しい気がしました。
バランスがよく、楽しめた作品ですが、大賞に推すのには何かもうひとつ足りない。それは何かというのを「スタンダードで破綻がないから」と書くとわかりやすいのでしょうが、この言い方は個人的にためらってしまいます。私自身、何度もそう言われてきましたし、得てしてこうしたストレートでアットホームな作風が戯曲賞で評価されにくいことも経験から知っています。
けれど登場人物ひとりひとりに愛情を注ぎ、丁寧にプロットを積み上げていくこと、細やかにユーモアを盛り込む努力もふくめて、評価したいと思いました。破綻がなくてもいいじゃないか、面白ければ、と、角のない丸い石を愛でるような気持ちで優秀賞に推しました。
ただ大賞に値する作品には、やはりもうひとつ強烈な何か、を求めてしまいます。なにかにめちゃくちゃ怒っているであるとか、気の毒なくらい傷ついているであるとか、作者個人の激しい衝動、あほみたいな欲望、禿げ上がるほどの執着、むきだしの赤い肉が見えるもの。
そんな作品にここでまた出会えることを期待していますし、私も描かねばと思います。